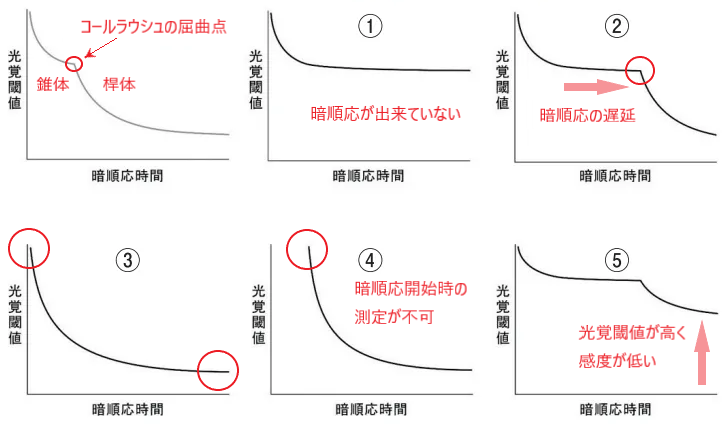 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 第51回午後、視能訓練士国家試験の解答と解説➋
どんな記憶でも、他の認知作業の干渉により一旦は意識から消えてしまいます。仕方がないことです。しかし、『記憶の定着』を行う為には、時間と共に減衰していく記憶情報の中から、定期的に保持情報を取り出す『検索練習』が欠かせません。そして、まとめて一...
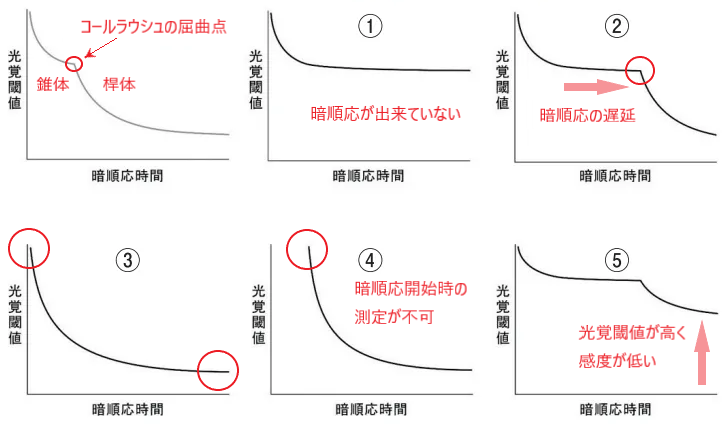 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題  眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 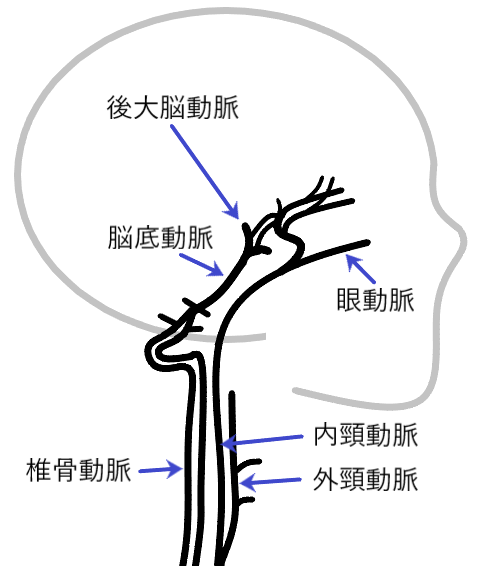 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 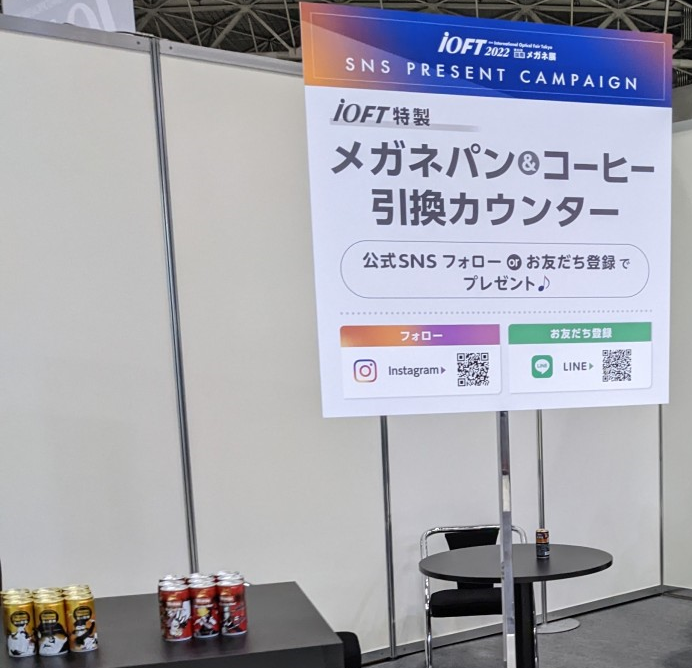 一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて
一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて 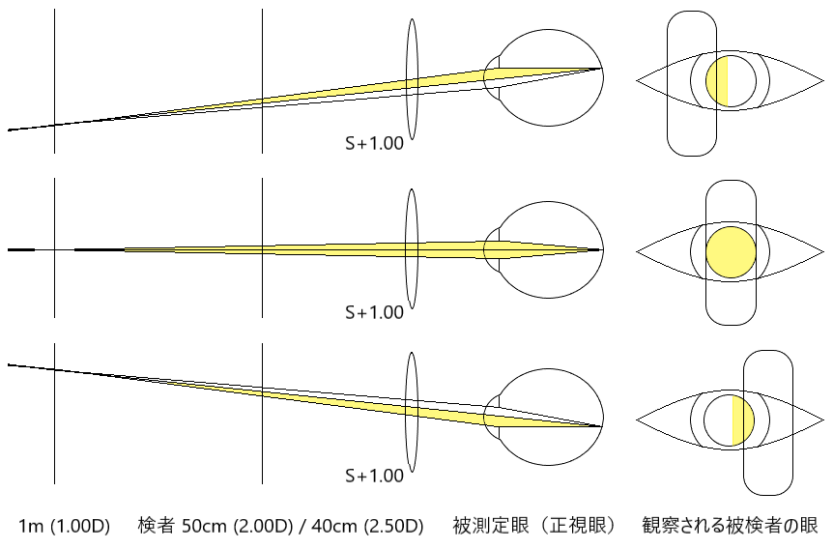 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 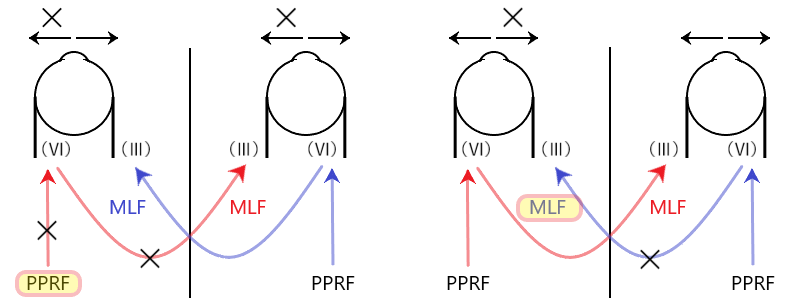 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 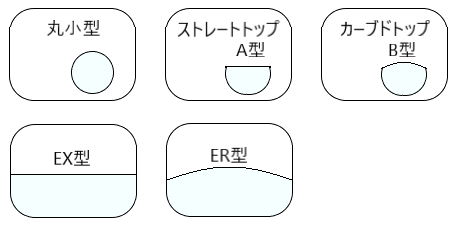 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 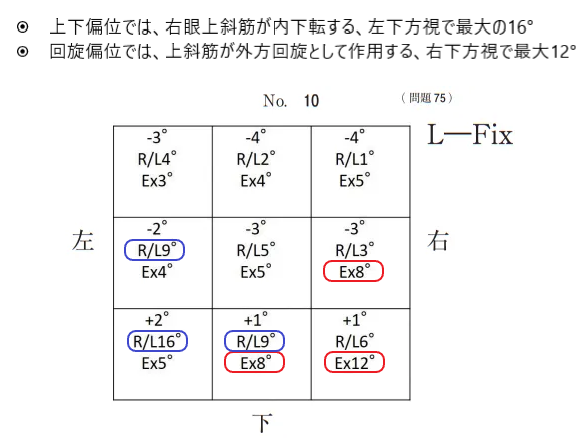 眼鏡作製技能士向けの問題
眼鏡作製技能士向けの問題 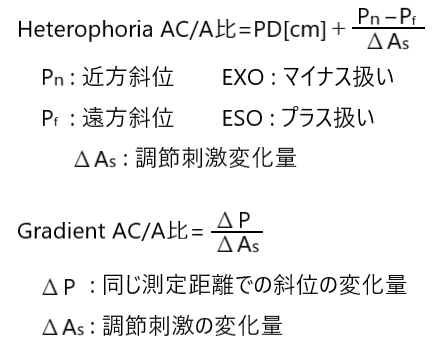 一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて
一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて 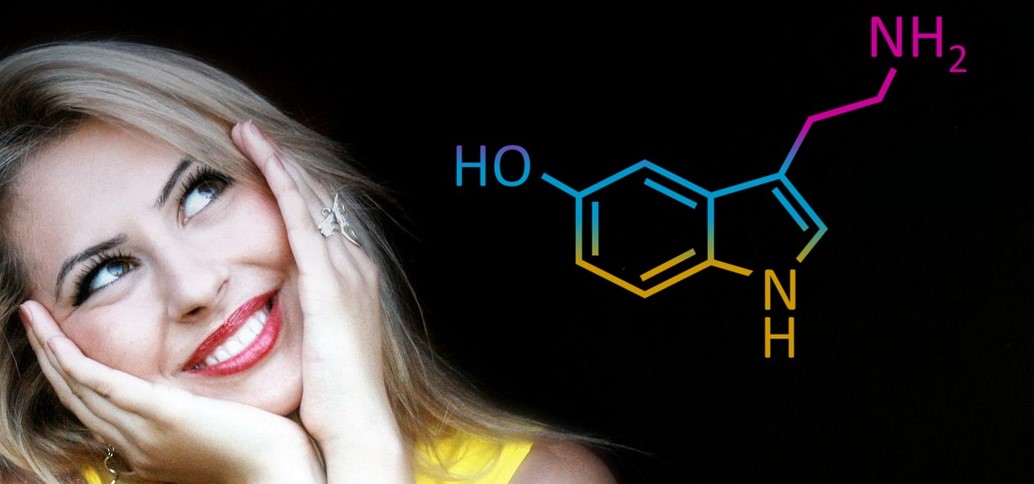 一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて
一般消費者、眼鏡作製技能士を志す方に向けて