Last Updated on 4年 ago by 管理者
瞳の色とは、つまり虹彩の色で決まります。
虹彩の色の種類
虹彩中のメラニン色素の割合で決まります。メラニンは紫外線から守る効果があります。
多いと『黒色』、少ないと網膜からの反射が多くなり『青色』や『赤色』になります。
- 色を混ぜることにより明るくなる光の混色(加法混色)
- 赤(R)、緑(G)、青(B)
- (例:R+G+B→白)
だったり、
- 逆に暗くなる色材の混色(減法混色)
- シアン(C)、イエロー(Y)、マゼンタ(M)
- (例:C+Y+M→黒)
のようですね。
- 様々な、虹彩の色
- ブラウン
- メラニン色素が多め
- 南ヨーロッパ
- アフリカ
- アジア
- メラニン色素が多め
- ヘーゼル
- メラニン色素は中程度
- レイリー散乱による
- アメリカ
- ヨーロッパ
- アンバー
- 黄色の色素沈着
- 狼
- 黄色の色素沈着
- グリーン
- メラニン色素は中程度
- 北ヨーロッパ
- メラニン色素は中程度
- グレー
- メラニン色素は多め
- ぶどう膜(虹彩、毛様体、脈絡膜)炎の兆候でも発生
- ロシア
- フィンランド
- バルト海沿岸
- ブルー
- メラニン色素は少ない
- レイリー散乱
- 光の波長よりも小さい粒子での散乱
- 例:空の色が青や赤
- 光の波長よりも小さい粒子での散乱
- 劣性遺伝
- ワーデンブルグ症候群でも発生
- アルビニズムでも発生
- 北ヨーロッパ
- 南ヨーロッパ
- レッド
- メラニン色素は少ない
- 網膜の血管が反射して透ける為
- アルビノ
- バイアイ、オッドアイ(虹彩異色症)
- 白猫に多い
- ブラウン
オッドアイ
オッドアイとは白猫に多くみられます。
『Odd』の意味である『奇数』が由来ですが、『奇妙』という意味もありますので、
『ヘテロクロミア(虹彩異色症)』や
『バイアイ』
が英語圏では使われます。
英語圏でのオッドアイとは『変な眼』という意味にもなる為、改められています。
『老眼(ろうがん)』を『老視(ろうし)』と呼ぶようにしているのと同じですね。
オッドアイと聞くと、難聴ではありませんでしたが、『名探偵コナン』の『純黒のナイトメア』のキュラソーを思い出します。
あとは、『黒子のバスケ』の赤司征十郎も思い出します。
人に現れた場合には、先天性のワーデンブルグ症候群(難聴など)や、
後天性のホルネル症(三大徴候:瞳孔縮小、眼瞼下垂、眼球陥凹)、虹彩毛様体炎、緑内障、虹彩萎縮などです。
虹彩の色が変わる食べ物!?
虹彩の色は、主にメラニン色素の量で決まります。
という事は、食べ物でも変化するかもしれません。
ビーガン(完全菜食主義者)は、お肉以外にも、卵や乳製品も口にしません。
そういった方の眼は、強膜は綺麗な白色で、虹彩には『緑色』が混じるという話しもあります。
蜂蜜、カモミールティー、ウワウルシ茶(クマコケモモ茶)、玉ねぎ、ほうれん草、生姜、ナッツ類、オリーブオイルなどを
5~6年ほど、根気よく食べ続けると変わるかもしれませんね。








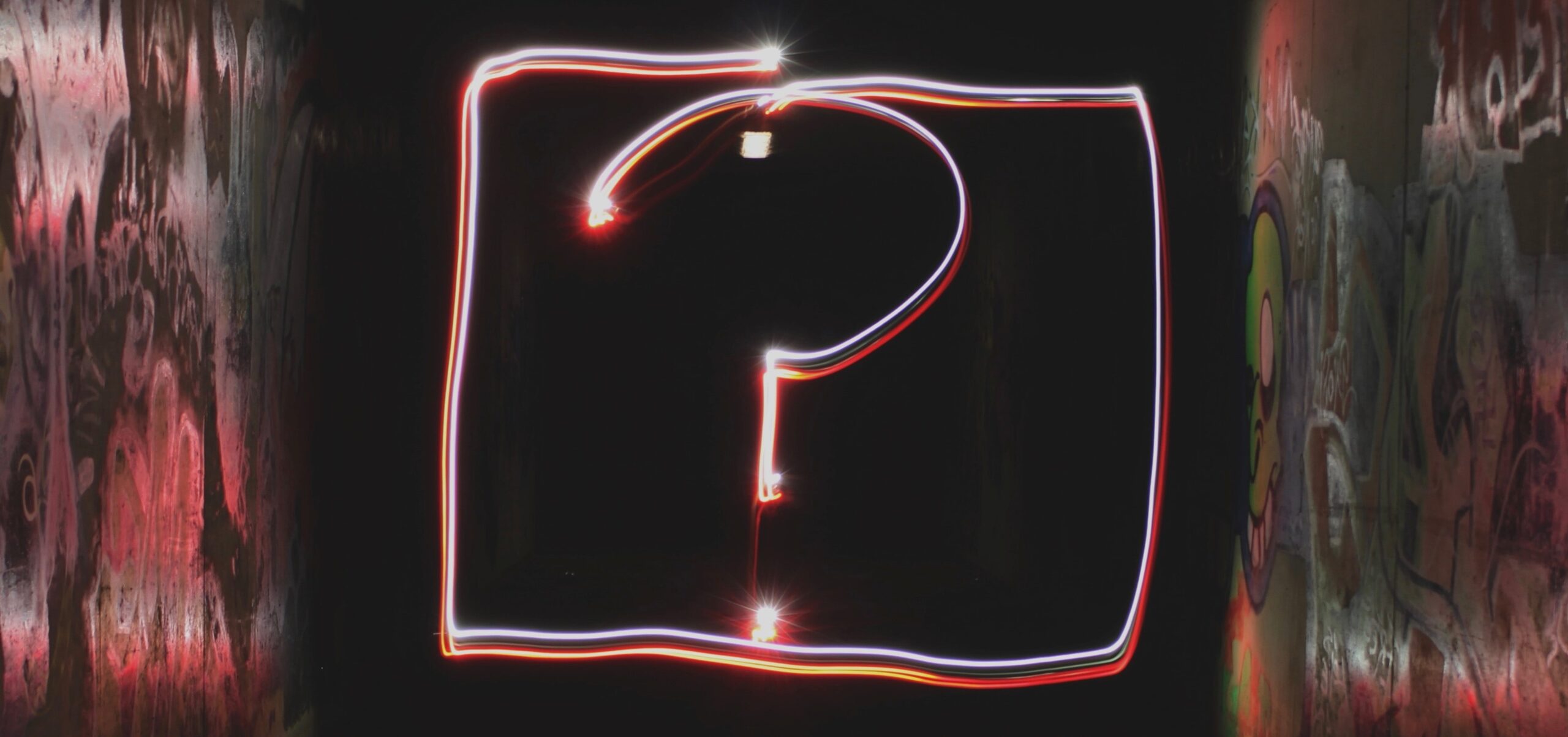
コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。